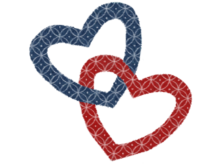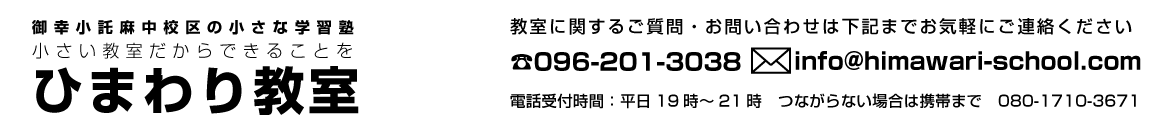熊本前期・私立面接必勝ポイント3つ(失敗から学んだ私の体験談)

「実は私、映画に出たことがあるんです!」
こう言うと多くの人に「すごい!」と驚かれるのですが、正直に言うと……その裏では“不合格の山”を築いてきました。
映画のオーディションには筆記試験はなく、すべてが“面接”のようなもの。
合格を勝ち取るためにどれだけ練習しても、それでも落ちまくるのが現実。とくに、私には光るものがなくって…よっ、この大根役者!
外国で生活していた時に役者活動していたので、言葉の壁で失敗することもありました。
シンプルな質問の意味すらわからないこともあれば、自分の答えが相手に正しく伝わっているのか不安で仕方ないこともありました。
それでも挑戦を続けていたからこそ、最終的には映画に出演するチャンスを掴めたんだと思います。
そして、その経験があるからこそ、高校受験の面接についてもお伝えできることがあります。
面接の基本は中学校の先生がしっかり指導してくれます。
ですので、ここでは「学校の先生とはちょっと違う角度からの、少し変わった面接のコツ」をご紹介したいと思います。
オーディションに落ちまくった人からの面接のアドバイスなんていらないかもしれないが、それでも一つ二つの合格を勝ち取るというのはすごいんだよ!って暖かい目で見てもらえれば嬉しいです。
① 第一印象は「3秒勝負」
オーディションでも面接でも、最初の3秒が命。
私の失敗談として、つかみは大事だろうと思っていて、オーディション会場に入るときに“受けを狙った登場”をしたことがあります。
ハローエブリバディー。アイム、パーフェクトアクター。これが私の使ってたツカミです。
キャスティングディレクターと知り合ったときに彼が言っていたのですが、そういう勘違いをする役者は意外と多いそうです。
入口はちゃんとした方がいい。
ウケを狙う必要はない。
ウケを狙って入室しても、面接官は愛想よく笑ってくれるので「つかみはOK!」って思っていたのですが、実際には心の中で「はいはい、またこのタイプね」と思われているそうで……。やっぱり最初は礼儀正しい方が印象に残るとのことでした。
高校受験の面接で言えば、次の3つ+笑顔が“最初の3秒”を作ります。
- 「失礼します」の発声
- ドアから椅子までの数歩の歩行
- 椅子に座るときの着座の姿勢
- 笑顔(この3動作に乗せる)
ここまでがだいたい3秒ほど。
この動作を笑顔に乗せて行うのは、実は結構難しい。
「挨拶・歩き方・姿勢・笑顔」——たったこれだけを意識するだけで、面接官は『この子は感じがいいな』と思ってくれて、自然とポイントアップにつながります。
歩き方や座り方の練習なんて普段しないですよね。私は役者時代にめちゃくちゃ練習しましたよ。
② 聞かれたことに答える
オーディションで「この役をどう表現したいですか?」といった質問をされることがあります。
そのとき、私はよく“自分の役者論”や“熱い思い”を語りすぎて空回りしていました。
「僕は演技を通じて人の心を動かす存在で〜」なんて熱弁しても、審査側の反応はイマイチ。
ところが、監督が作品に込めた思いや、台本から読み取れる意図を汲んで、
「自分はこう感じたので、こんな風に演じてみたいと思いました」
と答えたときの方が、会話が弾み、やり取りもスムーズになることに気づきました。
高校受験の面接も同じだと思うですよね。
「自分がこう思うから!」だけではなく、その高校の特色や教育方針を調べたうえで、
「だから私はこの学校で〜を頑張りたい」と答える方が、ぐっと説得力が増します。
一つの質問に対し、5秒くらいのシンプルさで、色々つけすぎてごちゃごちゃさせない。聞かれたことにシンプルに答えるがいいと私は思います。
③ 自然体が一番強い
映画オーディションではセリフを必死に覚えていったのに、本番で真っ白に。
でも、その時に出たアドリブの一言の方がウケが良かったりするんです。(その時の監督によりますが。)
受験面接も同じで、丸暗記はバレます。
練習は必要ですが、本番では“自分の言葉”が最強です。
ただし、「自然体でいい」と言っても、準備しているからこそ自然に見えるんです。
練習ゼロでアドリブに頼ると、ただのグダグダで終わります。
準備をしっかりして、その上で自然体を心がけましょう。
まとめ
「面接だけで合格できるなら楽勝じゃん!」とよく言われます。
もちろん、とりあえず受けてみるというノリでも全然いいと思います。
なぜなら、その挑戦が自分を大きく成長させてくれるからです。
当教室では、前期を受ける子への条件をひとつだけ設けています。
それは、「落ちても凹みすぎない性格であること」。
面接は不確かなものなので、誰でも落ちることがあります。
大事なのは、落ちても「また次!」と切り替えられる気持ちです。
その条件さえクリアできるなら、どんどん挑戦してほしいと思っています。
保護者の方にとっても「落ちたらどうしよう」という不安は大きいと思います。不安というか、自分の子供が傷つく姿を見たくない。そんな思いもあるかもしれなせん。が、
挑戦の経験そのものが必ず次につながります。
落ちても、その経験をバネに後期でしっかり結果を出す力が育ちますので、安心して見守っていただければと思います。