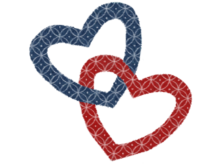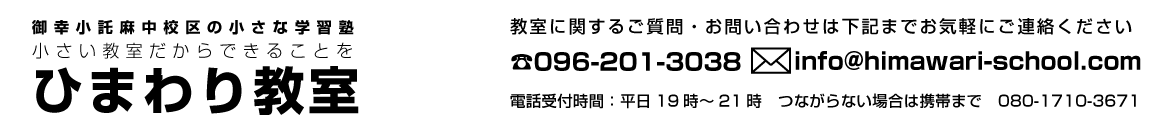中学生の勉強法:社会暗記が難しい!?
中学生の勉強法|社会の暗記が苦手な子へ
学習塾の現場から伝えたい「ちょっと楽になる覚え方」
社会という教科には、得意な子と苦手な子の差が大きく出ます。
- 社会が好きな子:「考えなくていいから楽」
- 社会が嫌いな子:「覚えることが多すぎて無理」
こういう声を、学習塾でもよく耳にします。
実際、社会が苦手な子の多くは、計算は得意だったりする傾向があります。
数学は、公式をひとつ覚えると似たような問題が解けるけれど、社会は用語や出来事、年号など、ひとつひとつを覚える量が膨大。
これが、勉強のしやすさ・しにくさに直結しているのです。
社会の暗記が苦手な理由、挙げてみると…
塾で生徒たちと話していても、「社会の暗記が苦手」と言う子には、こんな理由があります。
- 覚えきれない
- 覚えてもすぐ忘れる
- そもそもめんどくさい
- 授業がつまらない・先生が苦手
正直、4番目はどうしようもありません。ここでは、1〜3のタイプの子に向けて、「簡単そうに見える暗記法」をお伝えします。
暗記がちょっと楽になる方法
社会が苦手な子に共通しているのは、「最初から全部を覚えようとする」こと。
それだと、どこから手をつけていいか分からなくなり、結果として「もういいや」と投げ出してしまいがちです。
そこで、こんなふうに考えてみましょう。
ステップ①:「何を覚えたらいいか」を最初にしぼる
まずは、教科書やプリントに出てくる太字や赤字、先生が黒板に書いたことだけに集中します。
「全部覚える」ではなく、「最初は目立つものだけ」でOK。
赤シートで隠して覚えるのも王道ですが、それすらハードルが高いなら、まずは「声に出して読む」だけでも効果があります。
ステップ②:「つなげて覚える」を意識する
社会は、1つ1つの語句をバラバラに覚えようとすると大変ですが、物語のようにつなげると記憶に残りやすくなります。
例)
「鎌倉幕府ができた → 武士が力を持つ → 元寇が来る → 幕府が弱る → 南北朝時代へ…」
こんなふうに「流れ」で覚えることで、ひとつ忘れても前後で思い出せることが増えます。
ステップ③:「自分で小テストを作る」
自分で問題を作って、それを1日1回解くだけでも、記憶の定着率は大きく変わります。
例えば:
- 「平安時代の有名な人物は?」
- 「鎌倉幕府が始まった年号は?」
- 「参勤交代が始まったのはどの時代?」
簡単なクイズ形式にするのがポイントです。
最初は3問だけでも十分。「自分でつくる→自分で解く」が、意外に効くんです。
最後に
社会は「覚えるだけ」と思われがちですが、工夫次第で「思い出しやすくする」ことができる教科でもあります。
暗記が苦手な子ほど、「どうせ覚えられない」と最初から壁を作ってしまいがち。
でも、「ちょっとだけ覚えられた」「今日は3つ分かった」そういう小さな積み重ねが、自信につながります。
学習塾では、そうした「最初の一歩」を一緒に作ることを大切にしています。
社会の暗記に悩んでいるなら、まずは“覚え方”を変えることから始めてみませんか?